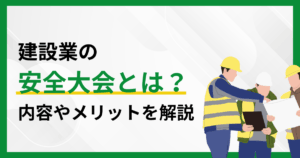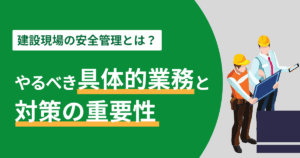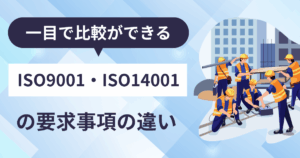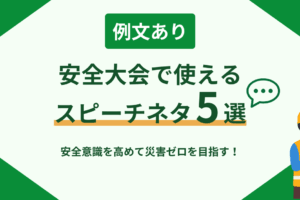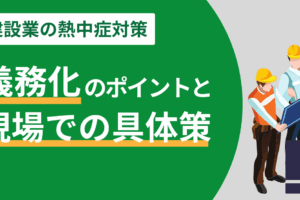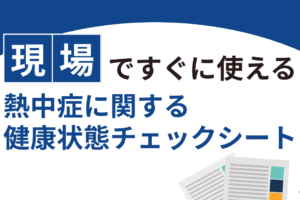建設業の熱中症対策|義務化のポイントと現場での具体策
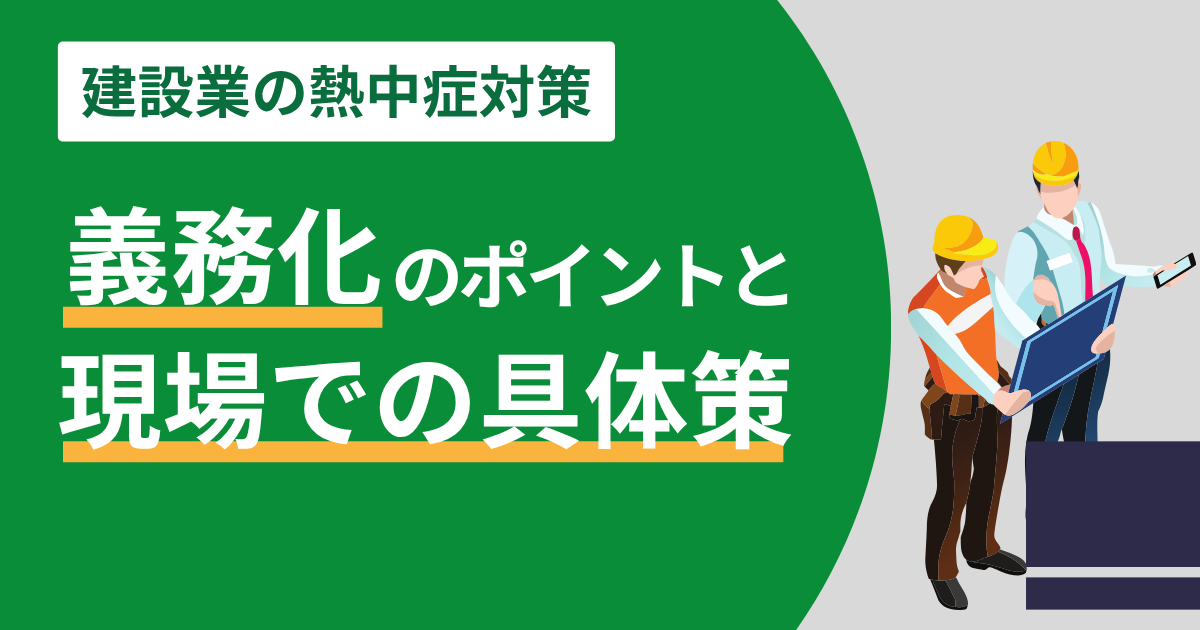
夏の建設現場では、熱中症が作業員の命を脅かす重大なリスクとなります。近年、その対策は企業の努力義務から法的な「義務」へと強化されました。
この記事では、建設現場の安全衛生責任者や管理者の方々に向けて、2024年から本格化する熱中症対策の義務化のポイント、厚生労働省のガイドラインに基づいた現場で実践すべき具体的な対策、そして万が一の際の対応まで、網羅的に解説します。
作業員の安全を守り、企業の法的責任を果たすために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
建設業における熱中症対策の義務化とは
建設業における熱中症対策は、これまでも重要視されてきましたが、近年の気候変動による猛暑の深刻化を受け、労働安全衛生規則が改正され、対策がより厳格に義務化されました。これは、作業員の命と健康を守るための重要な一歩です。
法的根拠と2024年からの変更点
熱中症対策の義務化は、労働安全衛生法および関連する労働安全衛生規則の改正に基づいています。特に2024年4月1日から、これまで努力義務だった多くの対策が法的な義務となりました。
主な変更点は、暑さ指数(WBGT値)の基準値を超えた場合の対策が具体的に定められたことです。具体的には、WBGT値の測定、休憩場所の整備、作業員への教育などが明確に義務付けられています。これにより、事業者はこれまで以上に計画的かつ具体的な熱中症予防措置を講じる必要があります。
(参考:厚生労働省「職場における熱中症予防対策」)
対象となる事業者と労働者の範囲
熱中症対策の義務化は、建設業を含むすべての事業者が対象です。企業の規模や業種に関わらず、労働者を一人でも雇用している場合は、この法規制を遵守しなければなりません。
対象となる労働者も、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイト、派遣労働者など、現場で作業に従事するすべての人が含まれます。元請け事業者は、下請け事業者の作業員も含めた現場全体の安全管理に責任を負うため、協力会社と連携した対策が不可欠です。
違反した場合の罰則規定
労働安全衛生規則に定められた熱中症対策の義務を怠り、労働災害(熱中症)を発生させた場合、事業者は労働安全衛生法第119条に基づき、「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
これは単なる罰金の問題ではなく、企業の社会的信用の失墜にも繋がります。作業員の安全確保は、企業の存続に関わる最重要課題であることを認識し、確実な対策を講じましょう。
現場で実践すべき具体的な熱中症対策
ここからは、厚生労働省のガイドラインに基づき、建設現場や工事現場で今すぐ実践すべき具体的な熱中症対策を「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」の4つの側面から解説します。
【作業環境管理】WBGT値の計測と低減措置
作業環境管理の要は、客観的な指標であるWBGT値(暑さ指数)を適切に管理することです。感覚だけに頼らず、科学的根拠に基づいた対策を行いましょう。
WBGT基準値と計測場所・頻度
WBGT(暑さ指数)とは WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは、気温、湿度、日射・輻射熱の3つを取り入れた、熱中症リスクを評価するための指標です。気温だけでなく、湿度や日差しの影響を考慮しているため、より実態に近い暑さの危険度を示します。
WBGT基準値 厚生労働省は、WBGT値に応じた作業の中止や休憩の目安を定めています。特にWBGT値が31℃以上の場合、運動の原則中止が推奨されており、建設現場のような過酷な環境では特に厳格な管理が求められます。
計測場所と頻度 WBGT値は、作業場所のできるだけ近く(高さ0.5m~1.5m)で測定することが重要です。直射日光が当たる場所と日陰では数値が大きく異なるため、複数の地点で測定することが望ましいです。測定は、少なくとも作業開始前、および1日のうちWBGT値が最も高くなる時間帯(10時、14時頃など)に定期的に行いましょう。
日よけの設置やミストシャワーの導入
WBGT値を下げるためには、物理的な対策が効果的です。
- 日よけの設置 作業場所にテントや遮光ネットを設置し、直射日光を遮ることでWBGT値を大幅に低減できます。特に、休憩場所には必ず日よけを設けましょう。
- ミストシャワー・ミストファンの導入 気化熱を利用して周辺の温度を下げるミスト装置は、休憩場所や風通しの悪い作業エリアで有効です。作業員の体を直接冷やす効果も期待できます。
- 送風機の設置 風通しを良くすることも重要です。大型扇風機や送風機を設置し、空気の流れを作ることで体感温度を下げ、汗の蒸発を促します。
【作業管理】作業時間と休憩のルール
作業管理のポイントは、暑い時間帯の作業を避け、こまめな休憩を確保することです。無理のない作業計画が、熱中症予防の鍵となります。
作業計画の変更と連続作業時間の上限
- 作業時間のシフト WBGT値が高くなる13時から15時頃の作業を避け、早朝や夕方に作業時間をずらすなどの柔軟な対応が求められます。
- 連続作業時間の短縮 高温多湿の環境下では、連続して作業する時間を短く設定し、作業の合間に短い休憩(小休止)を挟むことが有効です。
- 作業ペースの調整 WBGT値が高い日は、作業のペースを落とすよう作業員に指示し、身体への負担を軽減させましょう。
涼しい休憩場所の確保と定期的な休憩
- 休憩場所の条件 休憩場所は、日陰で風通しの良い場所であることが最低条件です。可能であれば、冷房設備のあるプレハブや車両、スポットクーラーを設置したテントなどを用意し、効果的に体を冷やせる環境を整えましょう。
- 定期的な休憩の徹底 作業員の自己判断に任せるのではなく、管理者が時間を決めて定期的に休憩を取らせることが重要です。喉の渇きを感じる前に、水分と塩分を補給する時間を確保してください。
【健康管理】作業員の日々のチェック体制
熱中症は、その日の体調に大きく左右されます。作業員一人ひとりの健康状態を毎日確認する体制を構築しましょう。
作業開始前の健康状態確認項目
毎日の朝礼時などに、以下の項目について作業員自身に申告させ、管理者が確認する習慣をつけましょう。
- 睡眠不足の有無
- 疲労感の有無
- 発熱、頭痛、吐き気などの症状の有無
- 前日の飲酒量
- 朝食の摂取状況
これらの項目に一つでも不安がある場合は、作業内容の変更や、場合によっては作業を休ませる判断が必要です。
体調不良者発生時の対応フロー
現場で「少し気分が悪い」「頭が痛い」といった体調不良を訴える作業員が出た場合は、絶対に無理をさせず、すぐに作業を中断させましょう。
以下の手順で、対応を行います。
1. 作業を中止し、身体を冷却する。
主な冷却方法は以下の通りです。
- ビニールシートによる全身冷却
- 水道水散布法
- 全身アイスタオル法 など
2. 救急車を要請するか、経過観察とするかの判断をする。
以下の症状がある場合は、速やかに救急車を要請してください。
- 意識がない
- 自力で水分が取れない
- 痙攣している
- 呼吸困難
- 嘔吐
一方、以下のような軽度の症状であれば、経過観察とします。
- めまい
- 頭痛
- 倦怠感
- 集中力がない
3. 状況に応じた応急処置を実施する。
【救急車を要請した場合】
救急車到着までに以下の対応を行ってください。
- 全身冷却
- 意識の確認
- 水分補給
- 救急車の通路確保
といった対応を救急車到着までに行ってください。救急車の現場到着までに10分以上かかるケースが全国で増加しています。数分が生死を分けるので迅速な対応を徹底しましょう。
【経過観察とした場合】
軽度の症状に対しては、以下の冷却方法を行います。
- 手のひらを冷やす「手掌冷却」
- 足を水に浸す「足水冷却」
4. 医療機関へ搬送する。
経過観察中に症状が改善しない、または悪化したときは、速やかに医療機関へ搬送をしてください。
初期症状の段階で迅速に対応することが、重症化を防ぐために最も重要です。
【労働衛生教育】実施すべき内容と頻度
熱中症対策は、作業員一人ひとりが正しい知識を持つことで、その効果が最大限に発揮されます。定期的な労働衛生教育は事業者の義務です。
熱中症の症状と予防法の周知
新規入場時や、夏本番を迎える前の安全大会などで、以下の内容について教育を実施しましょう。
- 熱中症の危険性とメカニズム
- 熱中症の具体的な症状(軽度~重度)
- 自己管理の重要性(睡眠、食事、水分補給)
- 熱中症対策グッズの正しい使い方
- 体調不良時の報告義務
緊急時の応急処置と連絡体制の教育
万が一、重度の熱中症患者が発生した場合に備え、全作業員が以下のことを理解している必要があります。
- 現場でできる応急処置の手順
- 救急車を要請する判断基準
- 緊急連絡先(管理者、事務所など)と報告フロー
実際に声を出して確認するなどの訓練を定期的に行うと、いざという時に冷静に対応できます。
工事現場におすすめの熱中症対策グッズ
法的な対策と合わせて、便利な対策グッズを導入することで、より効果的に作業員の安全を守ることができます。現場の状況に合わせて最適なものを選びましょう。
空調服・ファン付き作業着
小型ファンで衣服内に風を送り、汗を気化させて体を冷やす作業着です。今や夏の現場の必須アイテムと言えます。体力の消耗を大幅に抑え、作業効率の維持にも繋がります。バッテリーの持続時間や風量、耐久性を比較して選びましょう。
クールベスト・コンプレッションウェア
- クールベスト 保冷剤や水を含ませて着用するベストです。空調服が使えない場所や、より直接的に体を冷やしたい場合に有効です。
- コンプレッションウェア 体にフィットし、汗を素早く吸収・発散させるインナーウェアです。汗によるベタつきを防ぎ、気化熱で体温の上昇を抑える効果があります。空調服の下に着用するとさらに効果が高まります。
経口補水液・塩分補給タブレット
汗で失われるのは水分だけではありません。塩分やミネラルも同時に失われるため、適切な補給が不可欠です。
- 経口補水液 水分と電解質を素早く吸収できるように調整された飲料です。大量に汗をかいた後や、軽い脱水症状が見られる場合に特に有効です。
- 塩分補給タブレット・飴 手軽に塩分を補給できるアイテムです。水やお茶と一緒に摂取することで、効果的に熱中症を予防できます。
スポットクーラー・大型ミストファン
休憩場所や特定の作業エリアを局所的に冷やすための設備です。
- スポットクーラー 冷風をピンポイントで送ることができる移動式のクーラーです。休憩室や溶接作業など、熱がこもりやすい場所での使用に適しています。
- 大型ミストファン 広範囲にミストを噴霧し、周辺の気温を下げる大型の扇風機です。屋外の広い休憩スペースや、朝礼時の暑さ対策に役立ちます。
熱中症発生時の緊急対応マニュアル
どれだけ対策をしても、熱中症のリスクをゼロにすることはできません。万が一の事態に備え、現場の誰もが迅速に行動できるよう、緊急時の対応マニュアルを整備し、周知徹底しておきましょう。
現場でできる応急処置の手順
意識がある場合の応急処置は、以下の手順で行います。
- 涼しい場所へ避難 直射日光を避け、冷房の効いた部屋や風通しの良い日陰へ移動させます。
- 衣服をゆるめ、体を冷やす ベルトや上着を緩めます。濡らしたタオルや保冷剤を首の付け根、脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている場所に当てて、体温を効率的に下げます。
- 水分・塩分を補給 意識がはっきりしている場合は、経口補水液やスポーツドリンク、食塩水(水1Lに塩1~2g)を自分で飲ませます。
救急車を呼ぶべき症状の判断基準
ためらわずに救急車を呼ぶべき危険なサインは以下の通りです。一つでも当てはまる場合は、すぐに119番通報してください。
- 呼びかけへの反応がおかしい、意識がない
- 体がけいれんしている
- まっすぐ歩けない、立てない
- 体温が非常に高い(触ると熱い)
- 自分で水分補給ができない
医療機関への情報伝達と報告フロー
救急隊や医療機関には、以下の情報を正確に伝えられるように準備しておきましょう。
- 発生時の状況(いつ、どこで、何をしていたか)
- WBGT値などの作業環境
- 本人の症状の経過
- 現場で行った応急処置の内容
- 本人の既往歴や持病(分かれば)
同時に、社内の安全管理者や事務所にも速やかに第一報を入れ、指示を仰ぐ体制を確立しておくことが重要です。
すぐに使える熱中症対策の資料ダウンロード
厚生労働省や関連団体は、現場ですぐに使えるポスターやチェックリストなどの資料を無料で提供しています。これらを活用し、現場の意識向上に役立てましょう。
現場掲示用ポスター(注意喚起)
厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」サイトでは、熱中症予防を呼びかけるポスターがダウンロードできます。休憩場所や詰所の入口など、作業員の目につく場所に掲示しましょう。
(出典:厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」)
朝礼で使える安全教育資料
同サイトでは、朝礼やミーティングで使えるリーフレットも提供されています。熱中症の症状や対策を簡潔にまとめた資料を使い、定期的に注意喚起を行いましょう。
日々の健康管理チェックシート
厚生労働省の「職場における熱中症予防対策マニュアル」には、作業開始前の健康状態を確認するためのチェックシートの様式例が掲載されています。これを参考に、自社の現場に合ったチェックシートを作成・活用してください。
(出典:厚生労働省「職場における熱中症予防対策マニュアル」)
熱中症対策に関するよくある質問(FAQ)
最後に、建設現場の管理者からよく寄せられる質問にお答えします。
WBGT計は必ず購入が必要か?
はい、WBGT値の測定は義務化されており、測定器の準備は必須です。 ただし、必ずしも高価な測定器を購入する必要はありません。レンタルサービスを利用したり、比較的安価な簡易測定器を活用したりする方法もあります。また、環境省が提供する「熱中症予防情報サイト」でWBGT値の実況や予測を確認し、作業計画の参考とすることも有効です。
(参考:環境省「熱中症予防情報サイト」)
休憩時間に給与は発生するか?
労働基準法で定められた通常の休憩時間(労働時間が6時間超で45分、8時間超で1時間)は、原則として無給です。しかし、熱中症対策として事業者の指示で通常より長く休憩を取らせる場合や、作業を中断して待機させている時間は「手待ち時間」と見なされ、労働時間として給与支払いの対象となる可能性があります。労務管理の専門家にも確認することをおすすめします。
熱中症対策で使える助成金・補助金はありますか?
はい、あります。代表的なものに、高齢労働者のための安全衛生対策を支援する「エイジフレンドリー補助金」があります。この補助金は、空調服やクールベスト、ミストファンなどの熱中症対策用品の導入費用の一部を補助してくれます。申請期間や要件は年度によって変わるため、必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
(参考:一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会「エイジフレンドリー補助金」)
まとめ
本記事では、建設業における熱中症対策の義務化のポイントから、現場で実践すべき具体的な対策、おすすめのグッズ、緊急時の対応までを詳しく解説しました。
熱中症対策は、作業員の命と健康を守るための最優先事項であり、企業の法的・社会的責任でもあります。
この記事で紹介した内容を参考に、自社の現場に合った熱中症対策の計画を立て、実行してください。「WBGT値の管理」「こまめな休憩」「日々の健康チェック」「正しい知識の共有」を徹底し、安全な夏場の工事現場を実現しましょう。